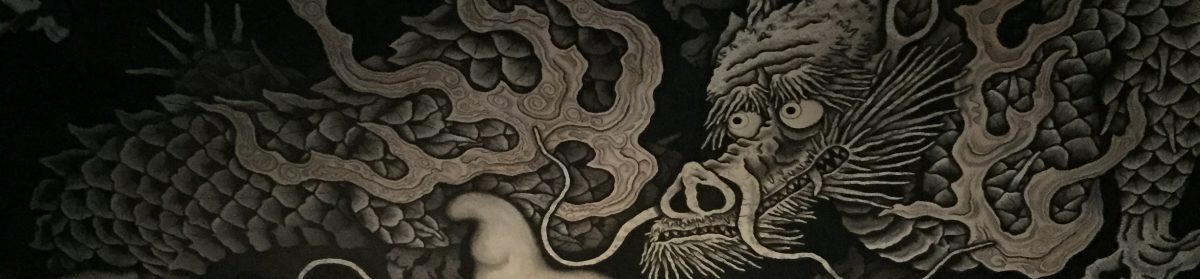目次
歴史遺産学研修6 (京都の祭)
明後日4月22日(土)、23日(日)と、初めて大学のスクーリングに行きます!
22日は瓜生山キャンパスで講義があり、23日は学外でのフィールドワークとして松尾大社に集合し、松尾祭を見学させて頂きます。
事前にテキストを読んで予習して、フィールドワークの準備をしているつもりですが、何しろ初めてなもので、色々まとめておこうと思います。
フィールドワーク準備
筆記用具
文化財を汚さない、傷つけないために、筆記用具は鉛筆(HB~2B)が必須となります。
ボールペンなどのインクが出る物は一切不可。シャープペンシルも不可です。
鉛筆は持ってなかったので、Amazonで鉛筆1ダースと、鉛筆削りを買いました。
(ご参考)
他に、ノート、クリップボード、カメラ(お持ちの方のみ)
キャラクトロジー講座の受講用に買ったクリップボードがあるので、メモはルーズリーフに書いて、後でまとめようと思います。
ダメとは書かれていませんが、iPhoneのカメラを使って良いならいいのでしょうか?
先生によって可不可違う可能性がありますね。
屋外用の服装及び雨具、帽子、飲み物など
この週末は好天に恵まれるようなので、雨具の必要は無さそうですが、暑さ対策が必要です!
わたしのように、普段引き篭もっていると、簡単に熱中症になりやすいですし、以前三十三所巡りをしている時にも大変な思いをした記憶があります。
動きやすい服装と、一日を通して歩いての移動になるので、履きなれたウオーキングシューズが良いですね。暑さ対策にタオル、帽子、ペットボトルは必須ですね。
ウォーキング用のリュックを担いでいかなければ。
(大事)Amazon Studentの登録
Amazonには学割制度があるので、登録資格があるなら必須です。
ちなみに、WEB上ではエラーになって登録ができなかったので、カスタマーサービスにメール申請したら、すぐに登録手続きができました。
早速、当面必要な参考書籍などを買いました。
参考書は汚くなければ古書で良いので、買い揃えようと思います。
科目概要と到達目標
平安京の成立以来、地域の成熟に従って京都の都市民は独自の祭礼をつくってきました。それは、農事を中心とした村の祭礼とはまた違ったもので、神輿と旅所をキーワードにし、その後の全国の都市型祭礼の先駆けとなりました。この授業は、教室の講義で、文献史料をもとに平安京の都市民の宗教的な諸問題と祭礼の成立について考え、フィールドでは実際に松尾祭の神輿渡御のようすを見学することで、知識と経験を有機的にリンクさせ歴史というものを実感し、学問の醍醐味を味わいます。到達目標は、歴史的なものの見方や史料を読み解く力を養い、またフィールド調査の要領を学び、史料とフィールドの連携を考えることです。
(シラバスより引用)
23日(日)に見学させて頂く「松尾大社」、「松尾祭」の神輿渡御について、事前に調べておく必要がありますわ。
『京都学』のテキストによれば、松尾大社の創建については、渡来氏族の「秦(はた)氏の祖霊崇拝の地として山上の磐座(いわくら)信仰から出発したものと考えられる。」とあります。
テキストの最初の第1章第1節が「渡来の人びと」というタイトルなもんですから、なんてタイムリーなスクーリングなんだろうと思いますね。
評価基準と成績評価方法
1. 授業の理解度(授業の趣旨を正しく把握し、理解しているか)
2. 学習姿勢・受講態度(授業をよく聴いているか、学外研修時にマナーやルールを正しく守ることができているか)
3. 授業への取り組み(フィールドワーク時に積極的に学習に取り組んでいるか)以上の評価観点を全体として満たしていることを合格の基準とし、主に授業への取り組みとスクーリングレポートによる評価とします。
(シラバスより引用)
講義のテキストが最初に配られるみたいです。
1年生の新参者ですし、最初は真面目なリジットが入ってしまうかもしれませんが、ぼーっとしないようにできれば前の方に座って、担当教授や他の参加者と顔馴染になりたいと思います。
予習・復習
参考文献のうち、京都市編『京都 歴史と文化2 宗教・民衆』(平凡社、1994年)の該当箇所を事前にみておくことをおすすめします。授業後は、配付した資料や現地でのフィールド調査を振り返り、授業内容を整理してしっかり復習してください。
(シラバスより引用)
この本は手に入れられなかったので、22日(土)にキャンパスの図書館で事前に確認しておく必要性がありそうです。
参考文献・URL
『京都学』本学テキスト
京都市編『京都 歴史と文化2 宗教・民衆』(平凡社、1994年)
柴田実『中世庶民信仰の研究』(角川書店、1966年)
五島邦治『京都 町共同体成立史の研究』(岩田書院、2004年)
(シラバスより引用)
著者にある五島邦治という方が、今回の担当教授です。
授業計画
●スケジュール
4月22日(土) 瓜生山キャンパス
2講時 講義:平安京の成立と都市の人々
3講時 講義:御霊会と平安京の祭礼
4講時 講義:松尾大社と松尾祭の歴史4月23日(日) 学外
10:00~11:30 学外研修:松尾大社楼門前(集合)→松尾大社(出輿見学)→月読神社→阪急「松尾大社」駅~阪急「桂」駅(一時解散)
11:30~12:30 昼食
12:30~17:10 学外研修:阪急「桂」駅(集合)→桂大橋東詰(船渡御見学)→(神輿と一緒に移動)→三宮神社(解散)● スクーリングレポート
1. 課題 :「現地見学を通して見えてくるもの」というテーマでレポートをまとめなさい。
*詳細は、授業の中で補足します。
2. 書式・文字数:ヨコ書き(ワープロ可 *テキスト科目のレポートの書式に準ずる)
1,200~2,000字程度
3. 提出締切日 :5月10日(水) 【必着】
4. 提出先 :郵送提出「通信教育部スクーリングレポート受付係」宛
窓口提出 瓜生山キャンパス人間館中2階 通信教育部事務局窓口
(窓口受付時間内)
※airUから提出する場合は、airUの課題をご確認ください。
(シラバスより引用)
22日(土)の講義は2講時からなので、キャンパスの教室に11:00までに行けば大丈夫です。
(事務局に確認済)
23日(日)の方が人が多くて電車が混みそうなので、早めに行って、ご朱印を頂きに行っておくくらいの余裕を持つ必要性を感じています。
レポート提出ですが、「airU」のシラバス内に、レポートを書いて提出する項目が無いので、紙で提出する必要があるかもしれません。
レポートの提出方法について、事務局に確認する必要があります。
自分メモ
松尾大社
松尾大社の公式サイト
http://www.matsunoo.or.jp/
こちらのサイトは良くできていて、松尾大社についての基本的なところは、ここで分かるようになっていますわ。
ウィキペディア(松尾大社)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E5%B0%BE%E5%A4%A7%E7%A4%BE
御霊会
3講時のテーマである御霊会(ごりょうえ)については、『京都学』テキストのP.29~30にもありました。
ウィキペディア(御霊会)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E9%9C%8A%E4%BC%9A
天変地異や疫病などの原因は御霊(=死霊、怨霊)とされ、祟りを鎮めるために御霊会を行なうようになったもの。
六所御霊
貞観五年(863)に神泉苑で御霊会が行われ、六柱の御霊が祭られた。六所御霊 と呼ばれている。
・崇道天皇(早良親王)・・・光仁天皇第二皇子、桓武天皇の弟で皇太子となるが、造長岡宮使・藤原種継暗殺事件に連座して乙訓寺に幽閉され、淡路に配流の途中憤死。長岡京から平安京への遷都の要因は早良親王の祟りとされる。
・伊予親王・・・桓武天皇第三皇子。伊予親王の変で謀反の嫌疑を受けて自害。
・藤原夫人(藤原吉子)・・・桓武天皇夫人で、伊予親王の母。共に自害する。
・橘大夫(橘逸勢)・・・書に秀で空海・嵯峨天皇と共に三筆と称される。承和の変で謀反の嫌疑を受け、伊豆へ配流の途中病没。
・文大夫(文室宮田麻呂)・・・承和の変に関係していたと考えられ、伊豆へ配流されて没したとされる。
・観察使(藤原仲成もしくは藤原広嗣)
(※)
『京都学』テキストでは観察使に当たる人物は藤原仲成とされ、八所御霊については触れられていない。
知識としては、八所御霊は現在、上御霊神社と下御霊神社に祀られている。
上御霊神社では、六所御霊に(火雷神と吉備真備)の2柱の神が追加され、伊予親王・観察使に替わって井上内親王、他戸親王が当てられている。
下御霊神社では、藤大夫として藤原広嗣が当てられる。
・藤原仲成・・・藤原種継の長男で、妹薬子が平城天皇の寵愛を受けて権勢を誇り、北陸道観察使に任じられている。薬子の変(最近は平城太上天皇の変というそうな)で失脚し、薬子と共に処刑される。
・藤原広嗣・・・藤原式家の祖、宇合の長男。左遷先の大宰府で反乱を起こし、処刑される(藤原広嗣の乱)
・井上内親王・・・聖武天皇第一皇女で、光仁天皇皇后。他部親王の母。光仁天皇を呪詛したとして皇后を廃され、大和国へ幽閉されて薨去。
・他部親王・・・光仁天皇皇太子。母の廃后に連座して皇太子を廃される。母と共に幽閉先で急死、暗殺説有り。山部親王(後の桓武天皇)を推す藤原式家による陰謀説が有力で、桓武天皇には兄弟の早良親王、他部親王の祟りが付き纏う。
神泉苑
神泉苑というのはあまり知らなかったので、ウィキペディアと公式サイトを見てみました。
神泉苑公式サイト
http://www.shinsenen.org/
ウィキペディア(神泉苑)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E6%B3%89%E8%8B%91
元々、大内裏の南に8町もの大きさのある禁苑(天皇のための庭園)であった。
貞観十一年(869)、南端に66本の鉾を立てて祇園社から神輿を出したのが、現在の祇園祭の元となっている。
ここまでお読み頂きまして、ありがとうございます。
ブログランキングに参加しています。お好きなバナーを押して頂けますと幸いです。